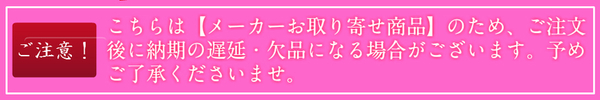
平成26年「消防団員服制基準」改正に対応!
カバー付き消防団ゴム長靴鉄製安全先芯・踏抜防止版・履口防水カバー標準装備!
ひび割れしないツヤ消し仕様、反射パイピングで視認性を確保!
素材:天然ゴム/合成ゴム
重量:約900g(26.0cm)
サイズ:24.0cm〜27.0cm・28.0cm・29.0cm
総丈:345mm〜380mm
カバー:60mm(防水加工品)
■樹脂の先芯、踏み抜き防止版を採用
踏み抜き防止版を採用しながら違和感のない
履き心地を確保し、
災害現場での長時間にわたる危険な消防活動をより安全にサポートします。
■異物の混入を防止
履き口に装備されたカバーにより異物混入を防ぎ、より円滑な消防活動をアシストします。
さらに60mmのカバーに防水効果を施すことにより、長靴内への水の侵入を最小限に抑えてくれます。
■踏抜き防止版・樹脂の先芯 標準装備
従来のゴム製長靴には、踏抜き防止版のみ装備の商品が多く、 カバーもなく、
防火用長靴としての使用用途に限られていましたが、このカバー付き消防団ゴム長靴は、
従来の踏抜き防止版に加え樹脂の先芯を装備、さらには履き口にカバーを装備していますので、
異物混入から足元を守り、災害現場での救助活動において使用が可能になりました。
■土砂災害現場では、編上げ靴だけでは対応できない…
近年多く見られる局地的な大雨による大水害、土砂災…。 現場がぬかるんだ状態での救助活動では
一瞬で足元は泥だらけに。編上げ靴では水、泥が靴内に侵入し、救助活動の大きな負担になります。
特に革製編上げ靴は、活動中だけでなく使用後に革がダメになり、その後使用不可能になるケースも多く聞かれます。
そんな現場ではこのカバー付き消防団長靴が水、泥の侵入を防ぎ危険な足元の環境からも踏抜き防止版、
鉄製安全先芯、履き口カバーにより保護してくれます。さらに使用後は水洗いができ、容易にお手入れができます。
従来のゴム長靴では成し得なかった、救助活動での使用が可能になります。
■救助用半長靴としての実績も多数。
従来のゴム長靴では「防火用」としての採用がほとんどでしたが、カバー付き消防団ゴム長靴は、
発売からわずか数カ月で多くの消防団様に「救助用半長靴」として採用をいただいております。